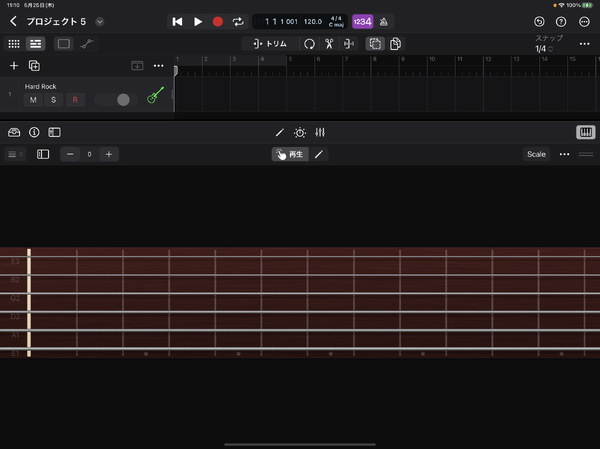Twitterのトレンドにこんなのが上がっていました。
本当のDTM

発端はこのツイート。「本当のDTM」をやってらっしゃる方がいたら、それがなんなのか答えを教えてください!、という問いかけによって、世の中のDTMerを巻き込んだ大喜利がスタートしました。
これは一言申さねばなりません。なぜなら、筆者は本当のDTMを体験した数少ない生き残りだからです。
DTM(Desk Top Music)という言葉を最初に使った製品が登場したのは、1988年のこと。PC-9801用のDTMパッケージ「ミュージくん」です。MIDI音源として、LA音源のMT-32、PC-9801用MIDIインタフェース、ダイナウェアが開発した五線譜ベースのソフトウェアをバンドルしたものでした。2020年度未来技術遺産にも認定されています。


▲ミュージくん
ちなみにDTMというのは、DTP(Desk Top Publishing)から発想したローランドのネーミング。MacintoshとページプリンタのLaserWriter、ページ記述言語の PostScript、ソフトウェアとしてはAldus PageMaker、Adobe Illustrator、Aldus FreeHandなどを駆使して、それまでは写植や活版もしくは高額なプリプレスでしか実現できなかったような印刷の前工程を、パソコンの画面で可能にするというDTPを、音楽制作に置き換えたのが、DTMでした。
詳しい話は以前ITmediaでコラムを書いているので、そちらも見ていただければ。
・DTMの夜明けを告げた「ミュージくん」とPC-9801がいたあの頃
こうした、コンピュータを中心に据えた音楽制作は、ミュージくんが初めてではありませんでした。Apple IIの時代から、そういったものはありましたし、ローランド自身、MIDI搭載シンセサイザーが登場する前に、パソコンを中心としたシステムを子会社経由で販売していました。
DTM以前
それが、CMU-800。筆者はこれも1982年の発売直後に購入して使っていました。CMU-800というのは、ドラム、ベース、ピアノ音源を内蔵し、CV/Gateインタフェースによって外部のシンセサイザーを制御できるという、ある意味、当時YMOが使っていたMC-4、MC-8を超える製品でした。当時のコンピュータは8bit機しかありませんでしたが、PC-8001、MZ-80、Apple IIといった機種用のソフトウェアと、制御用インタフェースがバンドルされて売られていました。価格は6万5000円と、コンピュータを持っていればおそろしく安価に入手できる価格帯だったのです。
筆者はMZ-80K2EとCMU-800、そして2台のシンセサイザーを使ってライブをやったこともあります。それが1982年のことでした。


▲MZ-80とCMU-800を操作する筆者と、ボーカルをとっている妻(1982年)
曲のエディットは、音の高さ、長さを数値でしていくステップ入力。現在主流のピアノロールとは程遠いものでしたが、MC-4やMC-8がわずかな表示部分しかないのに対し、パソコンの広い画面を使えるので非常に便利なものでした。
CMU-800は愛好家が多く、MIDIインタフェースを付けて音源として使えるようにしたものも出回っています。筆者が所有していたCMU-800は紛失してしまったので、新たにMIDI付きCMU-800を購入して手元にあります。

▲筆者が買い直したMIDI搭載CMU-800
このCMU-800を作っていたのはローランドの子会社だったアムデック。現在はローランドDGと改称されています。この頃には「コンピュータミュージック」という言葉はあったものの、別途、大掛かりなシンセサイザーを必要とし、「デスクトップ」と呼べるほどコンパクトなシステムではありませんでした。アムデックは、これをCompuMusicと呼んでいました。筆者も、MZ-80K2E、CMU-800の他に、MS-10、MS-20、System 100Mといった、当時としてはコンパクトだけどそこそこでかいアナログシンセサイザーをつなげる必要がありました。この辺りのことについても、別記事で書いているので、そちらをお読みください。
ちなみに当時筆者がCMU-800で作った例はこちら。
それから6年が経ち、16bitとなったパソコン(PC-9801)とそれに内蔵するMIDIインタフェース、そして、非常にコンパクトながらドラム、ベース、様々な音色を同時に奏でられ、しかも当時としては圧倒的にリアルなLA音源によるマルチティンバーを実現していたMT-32は画期的なものでした。メインマシンをPC-9801からMacintosh Plusに切り替えてもMT-32は使い続け、現在に至ります。

▲筆者所有のMT-32
これならなんでも作れるぞ、と筆者はローランド社員だった友人に頼み込んで入手し、夜な夜な耳コピで曲を作っていたのです。
それが長男が生まれた直後のこと。妻と子供の姿を追うホームムービーには、PC-9801VX2上でミュージくんのソフトウェアが動いているところも映っています。
そんなわけで、「本当のDTM」と言っていいのは、ローランドのミュージくん、そしてその後継であるミュージ郎だというのは強く主張していいのではないかと思います。
で、またシンセを買った
ところで、最初のシンセサイザーMS-10を買った大学1年生から45年経っても、新しいシンセがお手頃価格で出ると、欲しくなる衝動に駆られます。
先日ついつい買ってしまったのが、SONICWAREという日本メーカーのTexture Labという製品。2万9800円と安価でありながら、なんとグラニュラーシンセサイザーなのです。その名の通り、テクスチャー的なサウンドを作り放題。ノブもたくさんあって、ノブ1個当たりのコスパが鬼のように安い。これは近年稀に見る逸品でした。バッテリー駆動で、スピーカーも内蔵しているので、膝の上で無限に遊べます。
これだけで終わらないのがDTMの呪いでしょうか。別のシンセを買ってしまいました。
ベリンガーのARP 2600クローンです。8万3600円で、あのサウンドが手に入るなんて。
¥83,600
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
これを買うきっかけとなったのは、Amazon Primeビデオで視聴できるフランス映画「ショック・ドゥ・フューチャー」
1978年のパリ。YAMAH CS-80、ARP 2600といったシンセサイザーの名器が並ぶ一室で新しい音楽を作り出そうとしている若い女性の1日を描いたもの。そこにローランドのCompuRythm、CR-78が持ち込まれたことで転機が生まれるという話に、ワクワクせざるを得ませんでした。それでARP 2600って今どのくらいの値段なのかをAmazonで調べたのが運の尽き。上記のクローンシンセを買ってしまったのです。DTMerの魂百までという格言を提唱したいところです。歯止めが効かないと、下の写真のようになります。