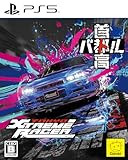Netflixのインタラクティブ映画『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』が、週明け5月13日にも視聴できなくなるようです。
『Black Mirror: Bandersnatch』(以下『バンダースナッチ』)は、ダークな英国産ドラマ『ブラック・ミラー』シリーズのクリエーターによるユニークな分岐型映像作品。
ブラック・ミラー: バンダースナッチ | Netflix(ネットフリックス)公式サイト
ネトフリ品質の映像で物語を鑑賞しつつ、主人公が何かを判断するタイミングで画面に選択肢が現れ、タップやリモコンで選択したとおりに物語が進むインタラクティブ映画です。
観ようとすると「5時間12分」と書いてあり腰を抜かしそうになりますが、これはすべての分岐を合計した時間のため。
実際のエンドクレジットまでの長さは、分岐にもよりますが60分~90分程度。短めの映画程度の時間で観られます。
週末の夜、これを観たら寝ようの体勢で鑑賞がおすすめです。
公式の番組説明は「1984年、ビデオゲームの開発チャンスを得た若いプログラマー。ファンタジー小説に基づくゲーム開発に取り組む中、現実とパラレルリアリティが混同し始める」。
グローバルで5月13日にはNetflixから削除される見込みのため、また体裁が体裁だけに別の媒体で見ることも難しいと考えると、『ブラック・ミラー』シリーズを見たことがある・興味があるならもちろん、全く聞いたことがなくても、非常にユニークな視聴体験ができる作品として、ぜひ一度は再生をおすすめします。

タイトルは『ブラック・ミラー』ですが、ドラマシリーズを見ていなくても全く問題なし。現在シーズン7まで配信中のブラック・ミラーも基本的には1話独立のアンソロジーなので、お話的なつながりや必要な予備知識はありません。
(逆にもしシリーズのファンでまだ見ていない場合、消える前にぜひ見てください。スタッフのお遊び的に他のエピソードとさりげないリンクがあったり、最新シーズンでは『バンダースナッチ』の登場人物が出てくるスピンオフ話もあります)。
『バンダースナッチ』を見るべき理由
色々とありますが、何より
・思いもよらない方向に連れてゆかれる、キテレツな視聴体験
・「分岐が選べる映画」をどう作るか?に対する鮮やかな回答
が楽しめるユニークな作品だから。
結末や展開が選べる物語作品は古くからありますが、最初から終わりまで一本道の作品とはまた違った展開の課題があり、分岐をどう活用するのか、視聴者をどう楽しませるのか、どんな体験をさせるかは文字どおり一筋縄ではいきません。
ネタバレにならない範囲でいえば、『バンダースナッチ』は主人公が「分岐型のアドベンチャーゲーム作りに没頭する若きプログラマ」というメタな舞台設定。
単なる「間違った選択肢でバッドエンド」や「プレーヤーが望む結末が選べます」に留まらない、思わぬ方向に視聴者を連れてゆく仕掛けを楽しめます。

「分岐が選べる」作品では、なぜ選ばされているのか、何を基準に選ぶことを期待されているのか、どちらが「正解」なのか戸惑うのもよくあります。
『バンダースナッチ』でも、最初はだから何だとしか思えない些細な選択を求められますが、物語が進むにつれて、あるいはひとつの結末を迎えたり、決定的な瞬間に立ち会うことで、選択にしだいに意味が生まれてゆき、受動的な鑑賞とはまた違う、上質なドラマとゲームの融合した没入感が味わえます。
分岐する物語という古くて新しいお題に対して、『ブラック・ミラー』シリーズのクリエーターとして人気のチャーリー・ブルッカーがどう答えを出したか、定番のネタも含めて「そう来たか!」という才気とケレンを楽しむだけでも価値あり。
・『ブラック・ミラー』シリーズと共通するダークで不穏な雰囲気 (若干視聴注意)
・「1980年代英国のホビーコンピュータマニア」時代描写の楽しさ
・主人公ステファン役のFionn Whiteheadはじめ、出演陣と映像の豪華さ
ドラマシリーズの『ブラック・ミラー』とは直接の物語的関係はなく、『バンダースナッチ』だけ観てもまったく問題ありません。
そのうえで、背筋がぞわぞわする不穏な感覚、ダークな展開はまさしく『ブラック・ミラー』節。
分岐によって物語が大きく変わり、なかにはややショッキングも展開があるため、ホラーやサイコサスペンス、ノワールが生理的に無理な場合、精神的なコンディションによっては、この作品に限らず視聴を考えたり、途中で離脱すべきかもしれません。

英国の1980年代ファッションや、なかでも黎明期のコンピュータゲーム界隈、ホビーコンピュータ等が描かれる時代描写も楽しめる点。
いわゆるホビーコンピュータは地域によって様々な機種が使われていたために、日本の同じ時期そのままではありませんが、8bit機の粗いピクセルで描かれるゲーム、壁のポスターや書籍、レトロな機器の雰囲気だけでも楽しめます。

主人公が使っている、虹のワンポイントがついたコンピュータは英国Sinclair の ZX Spectrum。日本では初代MSXあたりに相当する実在のホビーコンピュータです。
かなり小型でキーボード一体型スタイルのため、馴染みがないとあれがコンピュータ本体であることが分かりづらいかもしれません。
特に要らない仕様解説と予備知識、小ネタ
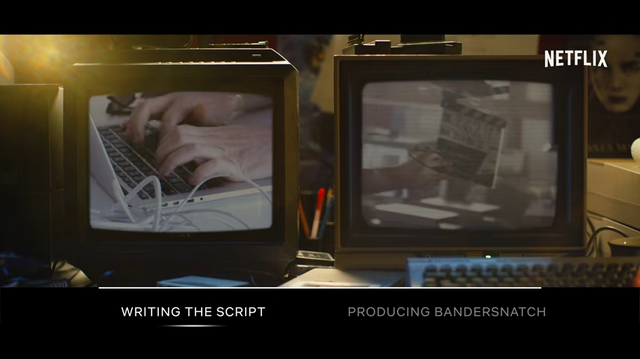
何を言ってもある種のネタバレになる作品で、とりあえず一回は通しで見て欲しいと願うばかりですが、ひとつ言えるのは「選択に迷うことも体験の一部」であること。
一般的な映像作品では視聴を止めたり飛ばすことはできても、意味ありげな選択を求められることはなく、その意味で選択に過大なストレスを感じる場合、特にどちらを選べば「正解」なのか分からない、選択後に正しいか間違いか分からずイライラするという人もいるかもしれません。
完全に向き不向きの話でもありますが、敢えて「心構え」的なものがあるとすれば、選択に唯一の正解はなく、正しい答えのヒントを読み取って当てるゲームではありません。
選択肢で運命がどう変わったのか、リアルタイムのコンピュータゲーム的にすぐ正解不正解のフィードバックが回るわけでもなく、不確定な世界である意味モヤモヤすることが前提の作品です。「そういうもの」と思って観ても気にならない視聴者向けという意味では人を選びます。
そのうえで、この作品の「仕様」的なものを述べると、
・選択肢はいつでも戻ってやり直せる
リニアに最初まで戻れる「早戻し」はありませんが、ある程度の範囲で、現在までの選択肢に遡ることはできます。操作は画面をタップまたはリモコンで、通常の早戻しと同じ。
ただ、なにかとんでもないことが起きても、それはそれとして分岐した物語が続くため、しくじったか?と思ってもすぐ戻る必要はありません。あとから戻れます。
・バンダースナッチってなんだよ??
特に知っておく必要は全くありませんが、作中でゲームタイトルとされるバンダースナッチ(Bandersnatch)は、『アリス』のルイス・キャロルが創造した架空のクリーチャー。
ルイスらしく、詩や小説で言葉遊び的に、敢えて具体的な描写を拒むようにチラッと描かれるだけなので、バンダースナッチがどんな姿なのかも(部分的な描写を除いて)特に一致した見解はなく、知らなくてもなんの影響もありません。
【ここから先、できればひと通り観てから進んで欲しいネタ】
.
.
.
・史実の『バンダースナッチ』
メタな話としては、現実の1980年代前半に、英国で期待のPCゲームとして大々的に宣言したあげくに発売されなかった幻のゲーム『バンダースナッチ』があり、今作はこのバンダースナッチをインスピレーションのひとつとしています。
(現実のバンダースナッチは発売されず、残骸を再生した別タイトルのゲームも、今作の『バンダースナッチ』とは全然別の内容です)。
・小エンドと大エンドがある(勝手に作った用語)
ある程度の段階で、選択肢によってはそこで物語が終わることがあります。
エンドは「2つ並んだTVモニターに以前の選択肢が映り、どちらかを選んで続行」になる場合(小エンド)と、「クレジットが流れてそのまま終わる」場合(大エンド)があり、敢えていえば、この「大エンド」が物語の結末です。
小エンドは多数、大エンドも複数あるため、違った結末を見ることを目的にした楽しみ方もあります。
・分岐は膨大
仕様的にややネタバレの範疇ですが、分岐は非常にたくさんあり、しかもシンプルな枝分かれだけでなく、いわゆる「フラグ」的なものもあります。(ある特定のシーンを見たかどうか等)。
これはかなり初期の段階で、小エンド後に物語を続けると、二巡目以降の主人公が体験していないはずのことが現在に影響を与えるといった展開で示されます。
もしコンプリートや他のあらすじを手っ取り早く知りたい場合、有志が解読したフローチャートもありますが、とても一見して把握できるものではなく、結末だけを見てもわけがわかりません。
ネトフリのインタラクティブ作品実験は終了。バンダースナッチが最後の2作品のひとつ
Netflix はある時期からインタラクティブ作品やゲームに近い作品を模索しており、看板作品のブラック・ミラーシリーズを使って作られたのが今作『バンダースナッチ』です。ほかマインクラフトテーマや、キッズ向けを含めいくつかの作品が作られました。
しかし方針的には、ネトフリの視聴アプリから遊ぶ/観るインタラクティブ映像ではなく、スマホのストアを通して既存の人気ゲームやオリジナル作品を提供し、ネトフリアカウントでログインすると遊べる方式に切り替えたため、インタラクティブ作品はカタログから段階的に削除されていました。
今作バンダースナッチと、もうひとつ『アンブレイカブル・キミー・シュミット』シリーズのスピンオフが最後の2作品。
この2つがグローバルで5月13日といわれる配信終了を迎えると、ネトフリの壮大な?インタラクティブ・ムービー実験は終わりを迎えることになります。
上記のとおり複雑なフラグ管理を含むこと、権利的にネトフリオリジナルであること、そして総計5時間を超えることを考えると、ネトフリがわざわざ別の形式で復活させない限り、今後は体験が難しくなることが予想されます。











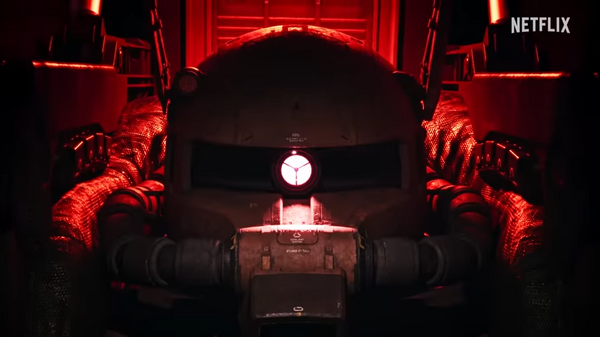












![【整備済み品】富士通 ノートパソコン 15.6型 初期設定済み A553/Office 2019/Win 11 Pro/WIFI/HDMI/Bluetooth/Celeron /メモリー4GB/SSD128GB [ PCステージ W.R.K ] image](https://m.media-amazon.com/images/I/51y84KsJkQL._SL160_.jpg)